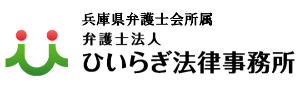遺産相続 トラブルのよくある事例と円満解決の対処法5つ

「遺産分割をしなければならないものの、相続人間でトラブルが発生してしまい、どうしたらよいのだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、遺産相続のよくあるトラブルと解決方法について解説します。
トラブル①~法定相続分と異なる割合での遺産分割
ある人(被相続人)が死亡し、遺産がのこされたとき、遺言があるときは遺言の記載に従って遺産分割をすればよいのですが、遺言がないときは相続人全員で話し合って遺産分割をすることになります(相続人同士の話し合いではまとらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停や審判によって解決することになります)。
法定相続人は、①配偶者相続人と②血族相続人の二種類に区別することができます。
このうち、配偶者相続人は1人だけであり、常に最も先順位の血族相続人と同順位の相続人となります(民法890条)。
これに対し、血族相続人には優先順位があり、先順位の血族相続人が誰もいないときに初めて次順位の血族相続人が相続人となります(民法889条)。
血族相続人の優先順位は、第1位が子とその代襲相続人(民法887条)、第2位が直系尊属、第3位が兄弟姉妹とその代襲相続人になります(民法889条)。
そして、重要なポイントは、民法は相続分についても法定しており、同順位の血族相続人の相続分は同じ割合であるということです。
例えば、被相続人の相続人として、妻・長男・二男・長女の4人がいるとします。
法定相続分は、妻が2分の1、長男・二男・長女が6分の1ずつになります。
つまり、遺言がない限り、「俺は後継ぎだから、弟や妹よりも多くの遺産を相続すべきだ」と主張することはできない(主張しても裁判所が認めることはない)ということになります。
このように、民法は相続分を明確に法定していることから、法定相続分を超える遺産を主張する相続人がいるとトラブルになります(相続人同士の協議や遺産分割調停では解決することができなければ、遺産分割審判にに移行することになるでしょう)。
トラブル②~相続人の1人が遺産を独占しているとき
 被相続人と同居していた相続人の1人(例えば長男)が自宅も預貯金も独り占めしている場合には、他の相続人(例えば弟や姉妹)と深刻なトラブルになります。
被相続人と同居していた相続人の1人(例えば長男)が自宅も預貯金も独り占めしている場合には、他の相続人(例えば弟や姉妹)と深刻なトラブルになります。
長男には長男の言い分(親と同居して死ぬまで介護をし家業も継いだ)もあるのでしょうが、遺言がないときには法定相続分に従って遺産分割をすることになります。
法定相続分は、長男も、その弟や姉妹も同じ割合になりますので、弟や姉妹より苦労をしたと考えている長男としては心情的に受け入れがたいものがあることでしょう。
被相続人が特定の相続人と同居したり家業を継がせたりしたので他の相続人より多くの遺産を相続させたいと考えるのであれば、他の相続人とトラブルにならないように、理由を明記した遺言をのこしておくべきだったといえます。
トラブル③~寄与分を主張する相続人がいるとき
相続人の中に「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」(民法904条の2第1項)人がいるとき、特別の寄与に応じて遺産を多く相続することができますが、他の相続人とトラブルになりがちです。
例えば、長男が親と同居して死ぬまで介護をしたケースで考えてみます。
長男の側からすれば、「弟や妹は親の面倒を見ずに好きにやっている。大変な苦労をしたのは俺たちだけだ」という不満を持っているかもしれません。
これに対し、他のきょうだいの側からすれば、「親の面倒を見ていると言うけど施設任せだし、遊びに行くといつも兄嫁の愚痴ばかり聞かされていたから、親身になって面倒を見ていたとは思えない。親に自宅を建ててもらって家賃の負担なくタダで住めただけでも親に感謝すべきだ」という不満を持っているかもしれません。
そのため、「特別の寄与」と評価できるほどの貢献があったかどうかをめぐって、きょうだい間で罵り合いが発生するケースも珍しくありません。
そこで、被相続人が特定の相続人から特別の貢献を受けたと思うのであれば、自分の死後に相続人間でトラブルが発生しないように、その旨を明記した遺言をのこしておくべきです。
トラブル④~遺産が自宅しかないとき
 めぼしい遺産が自宅しかなく、被相続人の死後も被相続人の配偶者がそのまま居住することを希望している場合には、自宅を売却してお金を分けることができません(被相続人と同居していた被相続人の配偶者は、被相続人の生前に、被相続人との間で配偶者が死ぬまで自宅に無償で居住できるという使用貸借契約を締結していたといえるため)。
めぼしい遺産が自宅しかなく、被相続人の死後も被相続人の配偶者がそのまま居住することを希望している場合には、自宅を売却してお金を分けることができません(被相続人と同居していた被相続人の配偶者は、被相続人の生前に、被相続人との間で配偶者が死ぬまで自宅に無償で居住できるという使用貸借契約を締結していたといえるため)。
このような場合には、被相続人の配偶者が死亡するまで待って売却し、そのお金を法定相続分に応じて分けるしかありません。
トラブルの元になりますので、被相続人が遺言をのこしておくべきケースといえます。
トラブル⑤~実子が知らない隠し子がいたとき
認知は遺言によってもすることができます。
また、被相続人が死亡した後は、検察官を被告として認知の訴えを提起することもできます。そして、遺言や判決によって認知された子は、実子と同等の血族相続人となります。
しかし、実子の側からすれば、被相続人の死後に突然きょうだいが増えたと言われても納得しがたいものがあることでしょう。
認知された子を交えて円満な遺産分割協議ができるとは思えず、トラブルを招くことになります。
そこで、被相続人としては、認知によって増えるであろう子の処遇を見据えた遺言をのこしておくべきだったといえます。
まとめ
このように、遺産相続には様々なトラブルが発生しますが、これらのトラブルの大半は遺言をのこしておけば予防することができます。
遺言の作成についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。