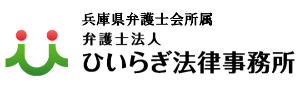被相続人とは?遺産相続の優先順位や遺言書の効力についてもわかりやすく解説!

「被相続人」とはどういう意味?
遺産相続の優先順位はどうなっているの?
遺言がある場合は?
ここでは、そうした疑問にお答えしたいと思います。
事例
ある日Aさんが亡くなりました。
Aさんが持っていた権利や義務は、死亡日にその一切が相続人全員に移転します。
すなわち、死亡した時に財産も借金もすべてが相続人のものになります。
仮に相続人がBCDであったとしても、この時点では不動産の権利はBに、預貯金はCになどと決まるわけではなく、BCDが法律で定められた割合で全体を承継します。
ここで相続においてよく使用する用語について解説しておきます。
上記の例で亡くなったAさんのことを「被相続人」といいます。
そして、被相続人死亡時点で法律上相続人となる人(上の例ではBCD)を「法定相続人」といいます。
さらに法定相続人が包括承継する法律上の割合のことを「法定相続分」といいます。
次に法定相続人なる人とその法定相続分についてみていくことにします。
まず、配偶者は別と考えます。配偶者は存在するのであれば必ず法定相続人になります。
次に法定相続人の順位は以下の通りです。
①被相続人の子供
↓子供がいなければ
②被相続人の直系尊属(親・祖父母など)
↓全員いなければ
③被相続人の兄弟姉妹
これ以降の順位はありません。
被相続人に配偶者がいない場合には各順位の相続人が頭数により相続します。
例えば、被相続人の配偶者がおらず子供が3人いる場合は1人3分の1の割合で相続することになります。
ところが、配偶者がいる場合にはこの相続分が変わります。
①配偶者と第一順位の相続人
配偶者 2分の1
第一順位 2分の1
となりますから子供が3人いる場合には、2分1を3等分しますから各6分の1となります。
②配偶者と第二順位の相続人
 配偶者 3分の2
配偶者 3分の2
第二順位 3分の1
③配偶者と第三順位の相続人
配偶者 4分の3
第三順位 4分の1
以上が法定相続分割合です。
何もしなければこの順序と割合で被相続人の権利義務を承継することになりますが、この相続分割合は絶対ではなく、民法にはいくつか承継方法を変更する方法が定められています。
法定相続分以外の承継方法
遺言
遺言とは、被相続人が生きている間に誰にどのような権利を承継させるかを書面に記しておき、原則として死亡を効力発生として、遺言書に記されたとおりに承継させる方法をいいます。
承継方法としては「不動産を〇〇に承継させる」と特定物を指定してもよいですし「相続分のすべてを〇〇に承継させる」というように包括的な内容でも構いません。
この場合に承継させる相手は法定相続人でなくても構いません。
特にお世話になった人に最後の贈り物として渡すことも可能です。
この場合、相手は相続人でありませんので、相続ではなく贈与の一種で「遺贈」といいます。
ただし、このようなことをされると法定相続人としては自分たちの取り分が少なくなる、あるいは場合によってはなくなるわけですから面白くありません。
そこで法定相続人には「遺留分」という最低限保証された割合について、他人や他の相続人に対して足りない額を返還請求できる権利が与えられています。
この遺留分は、第三順位の兄弟姉妹には与えられていません。
遺留分に相当する権利を法定相続人に残しておけば、遺言に記載したとおりに承継されることになります。
遺言作成については民法に作成方法が規定されていますから、無効にならないように要件をしっかり確認しなければなりませんが、公証人役場で作成する「公正証書遺言」の方法で作成すれば、無効になる恐れは極めて少ないです。
遺産分割協議
 法定相続人全員の話し合いで法定相続分をどのように変更しても構いません。
法定相続人全員の話し合いで法定相続分をどのように変更しても構いません。
各財産を特定した内容でもよいですし、全体的の相続分を決めても構いません。
ただし、全員の合意でなければならず、1人でも欠けている場合には無効になります。
遺産分割協議の結果は遺産分割協議書に記載して相続人全員が実印を押します。
法務局や金融機関に遺産分割の結果を提出して手続きする際は、遺産分割協議書に各相続人の印鑑証明書を添付します。
まとめ
今回は、相続について法定相続人および法定相続分割合について解説してきました。
今回の内容は、相続を理解する上での基礎となる知識ですので、これを理解していただきそれぞれの相続について承継方法を決める際に役立ててください。