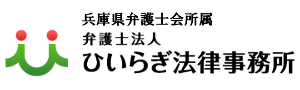遺産相続における遺留分とは?権利がある人とない人、相続割合や具体的な計算例を解説

最終更新日 2025年4月22日
「相続で遺産を受け取れないかもしれない」と不安を感じていませんか。
相続人が相続できる財産は、遺言書によって制限されるケースがあります。
しかし、民法では相続人の生活を守るため、遺留分という制度が設けられています。
遺留分とは、相続人に最低限保証された遺産の取り分です。
では、誰に遺留分の権利があり、遺留分の割合はどのように決まるのでしょうか。
この記事では、遺留分の基本的な仕組みから具体的な計算例、請求の流れまでを詳しく解説します。
相続トラブルを防ぎ、円滑な相続を実現するためにも、遺留分について正しく理解しましょう。
遺留分とは
 遺留分とは、相続人の生活を保障するために法律で定められた最低限の相続分です。
遺留分とは、相続人の生活を保障するために法律で定められた最低限の相続分です。
被相続人が遺言で財産の分配を決めても、一定の相続人には遺留分が保証されています。
遺留分制度により、相続人は遺言内容にかかわらず、最低限の財産を相続できる権利を持ちます。
遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。
ただし、自動的に相続されるわけではなく、相続人が請求しなければいけません。
このように、遺留分制度は被相続人の財産処分の自由と、相続人の生活保障のバランスを取る役割を果たしています。
遺留分の権利がある相続人
 ここでは、遺留分を相続する権利がある相続人について詳しく解説します。
ここでは、遺留分を相続する権利がある相続人について詳しく解説します。
配偶者
配偶者は、遺留分を相続する権利を持つもっとも重要な相続人のひとりです。
その理由は、婚姻関係にあった者として、被相続人と生活を共にし、財産形成に貢献してきた可能性が高いためです。
遺留分は、相続財産全体の2分の1のうち、法定相続分に応じて分配されます。
つまり、相続財産全体の4分の1が配偶者の遺留分です。これは、配偶者の生活基盤を守るために重要な役割を果たします。
ただし、内縁関係にある人は法律上の配偶者ではないため、遺言で指定しない限り、内縁関係にある人は相続権を持ちません。
直系卑属(子どもや孫)
直系卑属である子どもや孫は、遺留分を相続する権利を持つ相続人です。
子どもは第一順位の相続人として、被相続人の遺産を相続する権利を持ちます。
子どもがいない場合は、孫が代襲相続人として遺留分の権利を持ちます。
直系卑属の遺留分は、相続財産の2分の1の遺留分全体を、人数で等分した割合です。
たとえば、子どもが2人いる場合、それぞれの遺留分は相続財産全体の8分の1になります。
ただし、養子縁組をしていない連れ子や、認知されていない非嫡出子には遺留分の権利はありません。
直系尊属(親や祖父母)
直系尊属である親や祖父母も、遺留分を相続する権利を持つ相続人です。
ただし、直系尊属が遺留分権利者となるのは、配偶者も子どもも孫もいない場合に限られます。
直系尊属のみが相続人となる場合、遺留分全体は相続財産の3分の1です。
たとえば、両親が相続人の場合、それぞれの遺留分は相続財産全体の6分の1になります。
また、祖父母が相続人となるのは、両親がすでに他界している場合です。
直系尊属の遺留分は、被相続人の生前の扶養に対する報いや、高齢者の生活保障という観点から重要です。
ただし、養親には実の親の遺留分請求権はありません。
遺留分の権利がない人
ここでは、遺留分を相続する権利がない人について詳しく解説します。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分を相続する権利はありません。
これは、兄弟姉妹が被相続人と別々の生活を送っているケースが多く、生活基盤を共有していない可能性が高いためです。
法律では、より近い関係にある配偶者や子ども、親を優先的に保護する必要があると考えられています。
ただし、兄弟姉妹は法定相続人として、他の相続人がいない場合に相続権を持ちます。
遺言がない場合、兄弟姉妹は相続財産を均等に分割して相続できます。
しかし、遺言によって相続から除外された場合は、遺留分を請求できません。
相続放棄した人
相続放棄した人は、遺留分を相続する権利を失います。
相続放棄とは、相続人が自らの意思で相続権を放棄する行為です。
放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、遺産分割にも参加できず、遺留分も請求できません。
また、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
一度でも放棄をすると取り消しができないため、慎重に判断しなければいけません。
相続放棄をした人の子どもが代襲相続人となる場合もありますが、この場合、放棄した本人には遺留分の権利はありません。
相続放棄は重要な法的手続のため、専門家へ相談することが望ましいです。
相続廃除された人
相続廃除された人も、遺留分を相続する権利を失います。
相続廃除とは、被相続人や他の相続人が家庭裁判所に申し立てて、特定の相続人の相続権を剥奪する行為です。
廃除の事由には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあります。
認められると、その人は相続人としての地位を失い、遺留分を請求できなくなります。
ただし、厳格な要件が必要で、家庭裁判所の審判を経る必要があります。
また、被相続人が相続廃除の原因となった事実を知ってから1年以内に申し立てる必要があります。
遺留分の割合
 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
| 相続人の構成 | 遺留分全体の割合 | 各相続人の遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子:1/4(複数の場合は均等分割) |
| 子のみ | 1/2 | 子:1/2(複数の場合は均等分割) |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属:1/3(複数の場合は均等分割) |
配偶者や子がいる場合は遺留分全体が1/2となり、直系尊属のみの場合は1/3です。
各相続人の具体的な遺留分は、全体の割合を法定相続分に応じて分割して算出します。
遺留分の割合を正確に理解すれば、相続における権利を適切に主張できます。
遺留分の具体的な計算例
 ここでは、以下のような遺留分の計算例を解説していきます。
ここでは、以下のような遺留分の計算例を解説していきます。
| 父が遺した遺産総額が3,000万円。そのすべてを血縁関係のない人へ相続すると遺言があったが、納得いかずに遺留分を請求したと仮定した場合 |
それぞれの計算例を理解し、実際のケースに役立ててみてください。
相続人が配偶者と親だった場合
相続人が配偶者と親だった場合、遺留分全体の割合は1/2で、配偶者が1/3、親が1/6の遺留分を持ちます。
相続財産が3,000万円とすると、遺留分全体は1,500万円(3,000万円×1/2)です。
したがって、配偶者の遺留分は1,000万円(3,000万円×1/3)、親の遺留分は一人当たり250万円(3,000万円×1/6÷2)になります。
たとえば、遺言で配偶者に全財産を相続させると指定されていた場合、親は一人当たり250万円の遺留分侵害額を請求できます。
相続人が配偶者だけだった場合
相続人が配偶者だけだった場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/2です。
相続財産が3,000万円とすると、配偶者の遺留分は1,500万円(3,000万円×1/2)になります。
たとえば、被相続人が遺言で全財産を第三者に遺贈すると指定していた場合、配偶者は1,500万円の遺留分侵害額を請求できます。
相続人が子どもだけだった場合
相続人が子どもだけの場合、遺留分は相続財産の1/2です。
たとえば、相続財産が3,000万円で子どもが2人いる場合、各子どもの遺留分は750万円(3,000万円×1/2÷2)になります。
被相続人が遺言で一方の子どもにのみ財産を相続させると指定していた場合でも、もう一方の子どもは750万円の遺留分を請求できます。
相続人が配偶者と二人の子どもだった場合
相続人が配偶者と二人の子どもの場合、遺留分は相続財産の1/2で、配偶者が1/4、子どもたちで1/4を分けます。
相続財産が3,000万円とすると、配偶者の遺留分は750万円(3,000万円×1/4)、各子どもの遺留分は一人当たり375万円(3,000万円×1/4÷2)です。
たとえば、遺言で配偶者に全財産を相続させると指定されていた場合、各子どもは375万円の遺留分侵害額を請求できます。
相続人が親だけだった場合
相続人が親だけの場合(直系尊属のみ)、遺留分全体は相続財産の1/3です。
たとえば、相続財産が3,000万円で両親が相続人の場合、遺留分全体は1,000万円(3,000万円×1/3)となり、各親の遺留分は500万円(3,000万円×1/6)になります。
被相続人が遺言で第三者に全財産を遺贈すると指定していた場合でも、両親はそれぞれ500万円の遺留分を請求できます。
遺留分を請求する流れ
 ここでは、遺留分を請求する流れを詳しく解説します。
ここでは、遺留分を請求する流れを詳しく解説します。
戸籍謄本などから相続人を調査する
遺留分請求をするには、まず正確な相続人の把握が必要です。
戸籍謄本を取得し、被相続人の家族関係を詳細に調査します。
戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集しなければいけません。
これにより、法定相続人を正確に特定できます。
また、養子縁組や離婚歴なども確認し、複雑な家族関係を把握します。
相続人の中に既に亡くなっている人がいる場合は、その人の子どもが代襲相続人となる可能性もあるため、注意が必要です。
故人の財産をすべて調査する
遺留分請求をするには、被相続人の財産を正確に把握しなければいけません。
以下のような財産を徹底的に調査する必要があります。
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 生命保険金
- 貸付金
- 動産
財産調査には、金融機関への照会、不動産登記簿の確認、生命保険会社への問い合わせなどが必要です。
さらに、被相続人の生前贈与も遺留分算定の基礎財産に含まれるため、過去の贈与履歴も調べなければいけません。また、負債がある場合は、それらも確認します。
調査には専門知識が必要なため、弁護士や税理士などの専門家に相談するのが安心です。
相続人同士で話し合う
遺留分を請求する前には、相続人同士で話し合いを行うことも重要です。
遺言内容や財産分配についてお互いの意見を交換し、合意形成を目指します。
この段階で、遺留分侵害の有無や程度を確認し、可能であれば自主的な解決を図ります。
話し合いの際は、感情的にならず、冷静に事実関係を確認しましょう。
また、各相続人の生活状況や被相続人との関係性なども考慮に入れてください。
話し合いで合意に至れば、遺産分割協議書を作成します。
内容証明郵便の送付や弁護士への相談
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便の送付や弁護士への相談を検討します。
内容証明郵便では、遺留分侵害の事実と請求内容を明確に記載し、相手方に通知します。
これにより、正式に遺留分減殺請求の意思を伝えられるでしょう。
弁護士への相談は、法的な観点から事案を分析し、最適な対応策を検討するために有効です。
弁護士は遺留分請求の手続や交渉をサポートし、専門的なアドバイスを提供します。
遺留分侵害額の請求調停申立て
内容証明郵便の送付や弁護士を通じた交渉でも解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申し立てを行います。
調停では、遺留分侵害の事実確認や侵害額の算定、解決案の提示などが行われます。
訴訟に比べると柔軟な解決が可能で、当事者の関係性を維持しやすい点がメリットです。
ただし、調停は強制力がないため、相手方の協力が得られない場合は解決に至らない可能性があります。
遺留分侵害額の請求訴訟を行う
調停で合意に至らない場合は、最後の手段として遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
訴訟は裁判所が判決を下すため、法的拘束力のある解決が得られます。
ただし、遺留分侵害の事実や侵害額の立証が必要となるほか、専門的な法律知識が必要です。
訴訟提起後も和解の可能性はありますが、判決まで進むと時間と費用がかかります。
また、家族関係が悪化するリスクもあるため、慎重に検討しなければいけません。
まとめ
遺留分制度は、相続人の最低限の権利を保護する仕組みです。
配偶者、子ども、親などの近親者に遺留分の権利があり、割合は法律で定められています。
また、遺留分の計算や請求の流れは複雑です。専門知識が必要となる可能性が高いため、問題に直面した際は専門家のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
弁護士法人ひいらぎ法律事務所では、遺留分に関する相談から請求手続まで、幅広くサポートしています。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適な解決策を提案します。
遺留分問題で悩んでいる方は、お気軽にひいらぎ法律事務所にご相談ください。弁護士のサポートを受ければ、円滑な相続と家族の平和を実現できます。
最終更新日 2025年4月22日