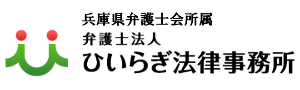生前贈与があると、遺留分侵害額の計算はどうなるのか?

最終更新日 2024年6月30日
生前贈与があると、遺留分侵害額の計算はどうなるのでしょうか?
被相続人が生前に相続人の誰かに自分の財産を贈与した場合には「もしその生前贈与がなければ相続財産はもっとあったはず」ということになります。
つまり、贈与を受けていない相続人からすれば不公平を感じることがあるわけです。
これは、よくある話であり実際に経験された方も多くおられるのではないでしょうか?
そこで、民法では「遺留分」という規定を設けています。
遺留分は、相続人に最低限保証される権利で、仮に被相続人が他の相続人に生前贈与や遺贈(遺言で贈与をすること)で全財産を譲った場合でも、遺留分を奪うことができません。
とはいっても、その生前贈与や遺贈が無効になるわけではなく、遺留分を持っている相続人が財産を譲り受けた相続人に後から遺留分を返還してもらうというものです。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
令和元年7月1日に施行された改正民法で「遺留分侵害額請求権」となりましたが、それ以前は「遺留分侵害請求権」という制度で、生前贈与や遺贈で譲られた財産そのものを取り戻す規定でした。
ですから、例えば不動産が贈与されたために遺留分が侵害された場合には不動産のうち侵害された割合の持分を取り戻すという制度でした。
ということは、遺留分侵害請求後の不動産は共有状態になるわけです。
これに対し、改正後は遺留分を侵害した「額」の請求ができることを明らかしたため、改正後に開始した相続については、不動産などの特定の財産の贈与や遺贈であっても侵害された額を請求できるようになりました。
今回はこれを踏まえて、改正された条文に沿って遺留分侵害額の計算方法を解説していきます。
全体の遺留分割合
まず前提知識の確認からしましょう。
「直系尊属のみが相続人の場合」
算定の基準となる財産総額の3分の1
「上記以外の場合」
算定の基準となる財産総額の2分の1
「兄弟姉妹が相続人の場合」
遺留分なし
個別の遺留分
 上記全体の遺留分割合で算出した額を各相続人の相続分割合を掛けることで相続人1人が持つ遺留分額が計算できます。
上記全体の遺留分割合で算出した額を各相続人の相続分割合を掛けることで相続人1人が持つ遺留分額が計算できます。
(例)
算定の基準となる財産総額が3000万円とします。
相続人が配偶者と子供2人のケースでは、直系尊属以外にあたりますから、2分の1である1500万円が全体の遺留分となります。
これに各相続人の相続分割合を掛けて個別の遺留分を算出します。
配偶者
1500万円×4分の2=750万円
子供1人
1500万円×4分の1=375万円
このケースの場合にはそれぞれこの額の遺留分を持っていることになります。
算定の基準となる財産総額の計算
 上記の例では、説明を簡単にするために算定の基準となる財産総額を3000万円としましたが、これを算出するための計算が最も複雑になります。
上記の例では、説明を簡単にするために算定の基準となる財産総額を3000万円としましたが、これを算出するための計算が最も複雑になります。
条文に沿って説明します。
(前提となる事実関係)
「被相続人死亡時に存在した財産総額」
3000万円
「被相続人の債務(借金等)総額」
400万円
「生前贈与」
3年前に配偶者に金銭500万円を贈与した
このケースで算定の基準となる額を算出してみます。
相続開始時の財産に遺贈または生前贈与の額を足します。
この場合に対象となる生前贈与は以下の通りです。
「相続人への生前贈与」
被相続人の死亡前の10年間にされたもの
「相続人以外への生前贈与」
被相続人の死亡前の1年間にされたもの
今回の事例では、3年前に相続人である配偶者に対してされた贈与ですからこれを足します。
3000万円+500万円=3500万円
次にそこから被相続人の債務(借金等)があれば差し引きます。
3500万円-400万円=3100万円
実際には金銭以外の財産の評価は複雑ですから、このような計算しやすい状態とは限りませんが、算定の基準となる財産額はこのように算出します。
遺留分の算出
相続関係は、配偶者B、長男C、次男Dとします。
直系尊属以外が相続人となるケースですので全体の遺留分は2分の1、1550万円となります。
B 1550万円×4分の2=775万円
C 1550万円×4分の1=387万5000円
D 1550万円×4分の1=387万5000円
となるのですが、ここからBが受けた生前贈与の額を差し引きます。
B 775万円−500万円=275万円
このようになります。
令和元年7月1日の改正民法により相続人への生前贈与は被相続人の死亡前10年間にされたものに限定されましたが、改正前は無制限で対象になっていました。
そして、この改正された規定は改正民法施行に開始した相続人適用されることになっていますから、相続開始が令和元年6月30日以前であれば、生前贈与のすべてが対象になります。
まとめ
今回は、生前贈与がある場合の遺留分の計算について解説してきました。
計算式としてはさほど難解なものではありませんが、実際の相続に際して財産額を評価・算定するのは一般的には困難です。
そのような場合には弁護士に相談してください。
最終更新日 2024年6月30日