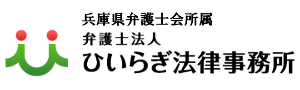遺留分を請求する方法は?請求後の手続はどうなるのか?亡くなった日による違い

最終更新日 2024年6月30日
「遺留分を請求する方法は?」
「請求後の手続はどうなるのか?」
「亡くなった日による違いはあるの?
今回は、そうした疑問に回答します。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に最低限保証される権利です。
例えば、被相続人が遺言で誰か特定の人にすべての財産を遺贈または相続させた場合には財産を承継できなくなる相続人が出てしまうことになります。
実際にこのような不公平な相続を経験された方もおられるのではないでしょうか?
このようなケースで、財産を受けることができなかった相続人は多く譲り受けた人に遺留分を返還請求できることになっています。
遺留分は、直系尊属(親・祖父母など)が相続人となる場合には3分の1、それ以外は2分の1、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合には遺留分はありません。
具体例を挙げて説明します。
(相続関係)
被相続人 A
相続人 B(妻)
C(長男)
D(長女)
(基準となる財産の額)
4000万円
この相続関係の場合には、直系尊属以外が法定相続人となるケースですから2分の1が遺留分となります。
すなわち、4000万円の2分の1で2000万円です。
次に、遺留分の返還請求はそれぞれの相続人が個別に行うことができる権利ですから、それぞれの遺留分を計算します。
法定相続分はB4分の2、C4分の1、D4分の1ですから先ほどの2000万円にこの割合を掛けると、
B 1000万円
C 500万円
D 500万円
となります。
基準となる財産の額とは
 上記の例は遺留分をイメージするために簡単に説明しましたが、計算の基となる額は以下の計算式で算出します。
上記の例は遺留分をイメージするために簡単に説明しましたが、計算の基となる額は以下の計算式で算出します。
「相続財産」+「一定の贈与の額」−「負債の額」=「基準となる財産の額」
「一定の贈与の額」というのは、以下の区分により判断します。
①相続人に対する贈与
→被相続人の死亡前10年間にされたもの
②相続人以外に対する贈与
→被相続人の死亡前1年間にされたもの
③被相続人と受贈者が相続人の遺留分を侵害することを知ってされた贈与
→贈与の時期に関わらず対象となる
※ただし、①については令和元年6月30日の改正民法で追加された規定です。
施行日以後に開始した相続に適用されます。
それ以前に開始した相続の場合には10年以上前の贈与も対象になります。
では、これらを踏まえて具体的に遺留分を算定してみましょう。
(相続関係)
被相続人 A
相続人 B(妻)
C(長男)
D(長女)
(相続財産)
不動産 評価額4000万円(土地3000万円、建物1000万円)
債務 300万円
(事実関係)
・遺言で土地をBに、建物をCに相続させる
・5年前にCに500万円を贈与
→相続財産が4000万円、生前贈与が500万円、負債が400万円ですから、4000万円+500万円−300万円=4000万円が基準となる財産額となります。
このケースでは、Dの受け取る分がないのでDが有する遺留分の割合を計算します。
4000万円×2分の1=2000万円
Dの法定相続分4分の1を掛けて、
2000万円×4分の1=500万円が遺留分となります。
つまり、Dが最低限受けとれるはずの財産が500万円不足していることになります。
遺留分侵害額請求
 上記の例でDは遺留分に不足している500万円を多くもらっているBとCに返還するように請求することができます。
上記の例でDは遺留分に不足している500万円を多くもらっているBとCに返還するように請求することができます。
では、どのようにしてこの侵害された遺留分を請求するのかを説明いたします。
令和元年7月1日に民法が改正されこの侵害された遺留分請求権の名称が「遺留分侵害額請求権」となりました。
改正以前は「遺留分侵害請求権」でした。
「額」という一文字が加わったわけですが、これは単に文字の問題ではなく実際に変更点ができました。
上記の例に従って解説します。
遺留分返還の対象となる贈与の順序
複数の贈与がある場合には、被相続人の死亡日に近い順に返還請求ができます。
遺贈は遺言によって財産を譲る行為ですから、死亡とともに効力が発生します。
ですから第一順位としては「遺贈」から請求し、それでも不足分に満たない場合には「死に近い順の生前贈与」を請求します。
そして、遺言の中で複数の遺贈がなされている場合には遺贈の額の割合で請求をします。
上記の例では、Bに遺贈されたのが3000万円、Cに遺贈されたのが1000万円ですからその割合は3:1となります。
Dが不足しているのが500万円ですからこれにその割合を掛けるとB375万円、C125万円ずつ請求できることとなります。
請求の手段は法律上規定はなく、口頭でも構いませんし手紙でも構いませんが、相手が簡単に返還に応じない場合には裁判の手続き等を利用することになるでしょう。
次にこれを令和元年7月1日(改正法施行日)前と後で比較します。
改正前に相続が開始した場合
改正前は、侵害された遺留分を遺贈や贈与された財産から取り戻すことになっていました。
したがって、上記の例では不動産ですから評価額に相当する不動産の持分の返還請求をします。
計算してみますと、Bへの返還請求が土地3000万円のうちの375万円ですから不動産の持分8分の1を請求することになります。
そしてCに対しては建物1000万円のうち125万円ですからこちらも建物の持分8分の1を返還請求できることになります。
改正後に相続が開始した場合
民法改正後は、特定物が遺贈や贈与されていた場合でも侵害された額の返還請求ができる
ことになりました。つまり、Dは、BとCに対してそれぞれ375万円、125万円の金銭を請求できることになりました。
改正前は例えば上記の例で不動産名義の8分の1を取り戻したとしても8分の7はBやCが所有しているわけですから全員が売却する意思がない限りお金を手元に残すことができませんでした。(8分の1だけを売却することはできますが、そのような不動産の一部の持分を買い取るのは専門業者に限られるでしょう)
このように改正前に相続が開始した場合とその後に相続が開始した場合とでは請求の仕方が異なってきます。
まとめ
今回は、遺留分についてその侵害された権利の返還請求について詳しく見てきました。
説明の中ではわかりやすくするために数字や財産、事実関係を簡潔にしましたが、実際にはもっと複雑になるでしょう。
遺留分侵害額請求をする場合には弁護士に相談されることをおすすめします。
最終更新日 2024年6月30日