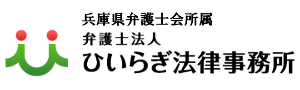特別受益に強い弁護士にききたい。この生前贈与は特別受益に当たる?当たらない?

最終更新日 2024年10月9日
- 特別受益に強い弁護士にききたい
- この生前贈与は、特別受益に当たる?当たらない?
ここでは、特別受益に強い弁護士に相談したい方へ、あなたが気になる生前贈与が、特別受益に当たるのか、それとも当たらないのかについて、説明いたします。
特別受益とは
特別受益とは被相続人の生前に贈与を受けるといった、特に生活上の援助を受けた相続人の相続分を他の相続人となるべく公平になるように調整する規定を指します(民法第903条)。
具体的には、以下のものが特別受益として扱われます。
生前贈与
生前贈与は、いろいろな目的をもって行われます。
生前贈与は将来遺産となる予定であった財産を先に渡すということになる場合には「先に遺産をもらった」と考えるのが公平性に資するため特別受益の対象となります。
以下にケースを分けて確認します。
- 婚姻時の援助
婚姻時に親から嫁入り道具や持参金として与えられた贈与はここにいう生前贈与にあたります。
- 養子縁組の際の援助
親が子どもを養子縁組に出す際にその持参金として与えた贈与は生前贈与にあたります。
- 生計の資本としての援助
開業資金、高額な大学の学費、留学資金、居住するための不動産の購入資金の援助などは原則として生前贈与にあたります。
ただし、通常、親の扶養の範囲内と評価される程度の援助は特別受益にあたらないこともあります。
遺贈
遺言で特定の相続人に対して贈与する内容を記載することができます。
これを「遺贈」といい、特別受益にあたります。
死因贈与
死因贈与も遺贈と同様に死亡と同時に特定の相続人に財産を贈与することをいいます。
遺贈との違いは、生前に双方の契約(意思の合致)をもって行われる点ですが、死因贈与も特別受益にあたります。
特別受益にあたらないもの
 既に少し触れましたが、親が子どもに援助をした場合でも「扶養の範囲内」と評価できるものについては特別受益にあたりません。
既に少し触れましたが、親が子どもに援助をした場合でも「扶養の範囲内」と評価できるものについては特別受益にあたりません。
ただ、下記のようなものはかならず特別受益にあたらないと決まっているわけではありませんが、あたらないケースが多いものといえます。
- 結婚式費用
- 通常の大学の学費
- 祝い金
- 小遣い金
また、20年以上連れ添った夫婦の一方が他方に対して居住用に供する不動産の贈与や購入資金の贈与については特別受益にはあたらないものとされます(民法第903条第4項)。
特別受益は相続財産に持ち戻して計算する
特別受益にあたる場合には、対象の財産を相続開始時の財産に持ち戻して計算します(民法第903条第1項)。
以下例を挙げてわかりやすく説明していきます。
- 被相続人のプラスの遺産に特別受益にあたる財産を加える
例えば、プラスの遺産が3,000万円として、特別受益の額が300万円とした場合は、3,000万円+300万円=3,300万円です。
これを「みなし相続財産」といいます。
- ②①のみなし相続財産に各相続人の法定相続分割合をかけてそれぞれの承継する額を計算する
相続人が、配偶者A、子どもがBCDと3人である場合の法定相続分は、Aが1/2(=3/6)、BCDが各1/6となります。
①で算出したみなし財産額に掛けると、Aが1,650万円、BCDがそれぞれ550万円となります。
- 特別受益を受けた相続人の相続分から特別受益の額を引く
Bが特別受益を受けたとした場合は、550万円-300万円=250万円となり、それぞれの相続人が承継する額はAが1,650万円、Bが250万円、Cが550万円、Dが550万円となります。
この場合は、Bが受けた特別受益の額をBの相続分から差し引いてもまだBの受ける財産は残りますが、特別受益の額によってはBの額がマイナスになることもあります。
ただ、この場合でもBはマイナス分を自分の財産から補填する必要はなく、単純にもらえる財産が0になると規定されています(民法第903条第2項)。
被相続人がこの持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合は、相続開始時に存在する財産を基準に考えればよく特別受益を考慮する必要はありません(民法第903条第3項)。
特別受益を考慮する必要が無くなった場合、計算も不要となります。
特別受益を主張するには
 特別受益を考慮した遺産分割協議をするには、誰がどの時期にいくらの財産を受けたかを明確にしなければ進まないこともあるでしょう。
特別受益を考慮した遺産分割協議をするには、誰がどの時期にいくらの財産を受けたかを明確にしなければ進まないこともあるでしょう。
比較的相続人の仲が良い場合は、そこまでする必要もなくだいたいで話し合いがまとまることもあると思います。
しかし揉めるようなケースではなるべく具体的な資料を提示して話し合いを進める必要があります。
おわりに
特別受益は、対象となるか否か、その額などの判断も難しく自分で主張するのが困難な場合が多いです。
遺産相続にあたり他の相続人の特別受益を主張する際は、遺産相続に強い弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。
最終更新日 2024年10月9日